
こんにちは、最新の “お役立ち情報” をお届けする[Recommend Style]の横山です。
このページでは予備試験の基礎知識化から始まって、予備試験対策として評価が高いお勧めの予備校!
……アガルートアカデミーをご紹介させて頂きます。
予備試験の予備校に興味をお持ちの方は、どうぞ参考にしてください。
★☆★ 予備試験とは ★☆★
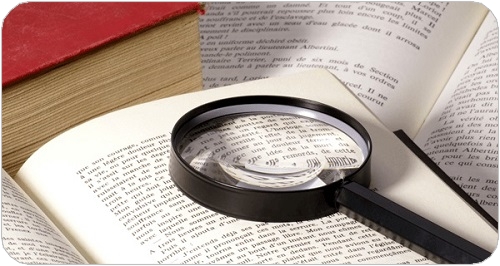
司法試験法の5条に
「法科大学院を修了者と同等の学識及び、その応用能力並び法律に関する実務の基礎素養を有するかどうかを判定する」
という条文があります。
この条文にあるような基礎知識を持った者しか司法試験は受験できません。
現在司法試験を受験するためには、法科大学院を卒業するか、予備試験に合格するかの二つの道があります。
予備試験の正式名称は「司法試験予備試験」で、司法試験法5条にあるような学識やそれを応用する能力を持っているか、法律に関する基礎的な実務の素養があるかを判定するために行われます。
法科大学院を卒業するには、まず大学院に入るための試験を受験しなければなりません。
修了までは、既修者で2年間、未修者で3年間かかるため時間やコストがかかる傾向があります。
それに対して予備試験は、受験資格は設けられておらず誰でも受験することができます。
一度で合格すれば、司法試験を受験するまでの時間やコストの負担を少なくすることも可能になります。
あくまで司法試験を受験する資格を得るためのものですが、非常に難易度が高く、かなりの努力が必要です。
しかし、正しい学習計画のもとで勉強していけば合格できる試験でもあります。
予備試験対策の予備校もあるので、効率よく知識を身に着けることができます。
この試験によって、多くの人が司法試験を受けるチャンスを与えられています。
また、司法試験は法科大学院終了後もしくは予備試験終了後5年で5回という受験期間が設けられていますが、予備試験には受験期間は設けられていないため、何度もチャレンジが可能です。
法科大学院に通うには時間的、コスト的に厳しいという人や、働きながら司法試験を受験したいというような人にとって予備試験は、たくさんのメリットがあるのではないでしょうか。
多くの人に受験の門戸を広げているこの試験は今後主流となっていくことが考えられます。
★☆★ 法曹三者(裁判官,検察官,弁護士)の業務 ★☆★

裁判官、検察官、弁護士はあわせて法曹三者と呼ばれています。
テレビなどを通して、それぞれの仕事になんとなくのイメージを持っている方も多いと思いますが、具体的に法曹三者にはどんな業務があるのかは、意外と知られていません。
【裁判官】
まず裁判官ですが、主な仕事は民事・刑事裁判において被告人が有罪か無罪か判断し、有罪の場合はどのような刑罰をくだすかも判断します。
民事では話し合いでは解決できないトラブルを法律と自らの良心に従って、適切に解決へと導きます。
刑事では検察官の主張・立証、弁護人による弁護活動をうけて、被告の有罪・無罪・刑罰を判断していきます。
自らの判断によってトラブルが解決されたり、当事者の今後の人生に関わってくる仕事なので、責任の重さと同時にやりがいを感じる仕事です。
【検察官】
検察官の主な仕事は、犯罪の被疑者を起訴するか否かを決定することです。
起訴した場合は、被告人の正当な処罰を求めて裁判所に立証や主張を行います。
犯罪の被疑者を逮捕するのは警察の仕事ですが、被疑者を罰するためには起訴し、裁判の場で有罪の判決を得なければなりません。
警察はこの権限を持っておらず、検察官だけが唯一被疑者を起訴するか否かの権限を持っています。
被疑者が起訴され被告人となった場合は、被告人の有罪を主張・立証し適切な刑罰を求めることも大切な仕事です。
そして、検察官は適切な刑罰を受けた被疑者や被告人らの社会復帰を支援することも認められています。
正義のもとで社会の平和を守るという仕事には、大きな達成感とやりがいがあります。
【弁護士】
弁護士の主な仕事は、民事裁判での訴訟代理人や刑事裁判での被疑者・被告人の弁護活動です。
裁判官や検察官と異なる点は、紛争の始まりから終わりまで介入し、解決の際は依頼人から直接感謝されるということです。
より人との関わりが多く、依頼者と密に接するということにやりがいを感じている者が多い仕事です。
★☆★ 予備試験のルーツ ★☆★

現在行われている司法試験は、法科大学院卒業か予備試験に合格した者が受験資格を持ちますが、平成23年度に廃止された旧司法試験は、1次試験に関しては基本的に受験資格は設けられていませんでした。
大学に在学中の学生も受験できたため、数多くの受験者がおり、ピーク時では約5万人ほどの受験者がいました。
門戸が広いため、高校生が1次試験を通過して話題になったこともありました。
現在の司法試験が、法科大学院または予備試験終了後5年で5回という回数制限が設けられているのに対して、旧司法試験は受験回数に制限がなかったため何度でも受験することができました。
なかには社会人を続けながら、10年以上チャレンジし続けるというようなケースもありました。
現司法試験は、受験回数制限に加えて、はじめの受験資格にも決まりがあるので、誰でもやみくもに受け続けるということは出来なくなっています。
受験資格のひとつである法科学院ですが、基本はフルタイムで通学しなければなりません。
仕事をしながら通っている法科大学院の数は極まれなので、社会人を続けながらの通学はハードルが高いと言えるでしょう。
こうしたことから、誰でも受けられる予備試験に合格して、それから司法試験の受験資格を得ようとする者が増加している傾向があります。
例えるなら、高校を卒業していなくても、高校卒業資格を得られる大学入学資格検定(大検)に合格して大学を受験するというようなことです。
予備試験の合格率は約3パーセントと非常に難易度の高いものですが、しっかり知識をつけて予備試験を通過した者の司法試験合格率は非常に高く、6割を超えています。
それぞれの環境や勉強のスタイルに応じて法科学院に通うのか、予備試験突破を目指すのかを選択すると良いでしょう。
★☆★ 法曹三者(裁判官,検察官,弁護士)になるには ★☆★

法曹三者になるためには、司法試験突破後に約1年間の司法修習を経て、司法修習生考査に合格する必要があります。
第一関門となる司法試験は、1年に1度、5月の中旬に5日間かけて行われます。
この試験は論文式試験とマークシート方式で行われる短答式試験からなります。
論文式試験の試験科目は、憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・選択科目で、短答式試験の科目は民法・憲法・刑法です。
司法試験の合格率は約20パーセントと低く、受験資格も設けられているため非常に難易度の高い資格となっています。
9月上旬に合格発表があり、合格すると司法修習生の資格が与えられ、1年間の研修期間に入り、実務を学んでいきます。
司法修習期間の終わりに司法修習生考査(通称2回試験)を受験し、それに合格して初めて法曹三者になることができるのです。
法曹三者のうち裁判官へのルートは特に狭き門と言われており、希望していても簡単に任命されるものではありません。
中立的な立場で物事を判断する特性や、謙虚な姿勢と思いやりのある心など、勉学以外の日ごろの素行や生活態度も問われてくるでしょう。
検察官になるには、法務省が実施する採用試験に合格して、検察庁から採用されなければなりません。
検察官の仕事は法廷で公正な裁きがくだせるよう、高潔さと不正をゆるさない強い正義感が求められます。
弁護士が裁判官や検察官と大きく異なるのは、民間人という立場だということです。
司法修習終了後弁護士志望者の大多数は、法律事務所へ就職します。
各事務所によって得意分野や取扱分野が違うため、将来的にどういった仕事をしていきたいかをよく考えたうえで就職活動をすることが大切です。
また、弁護士資格を生かして企業の法務部などで活躍するなど選択肢が多いのも特徴的です。
★☆★ 予備試験の試験情報 ★☆★

予備試験は、短答式試験・論文式試験・口述試験の3つからなっています。
【短答式試験】
短答式試験は5月の中旬の1日、論文式試験は7月上旬の2日間、口述試験は10月下旬の2日間に行われます。
これらはひとつずつ順番に合格しない、と次の試験を受けることができません。
10月の口述試験まで、3つすべて合格すると最終合格となり、翌年の司法試験受験資格を得られるのです。
短答式試験はマークシート形式で、複数の選択肢の中から問題文に指定されたものを選んで回答します。
試験科目は、憲法・民法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法・商法・行政法・一般教養の8科目です。
270点満点で一般教養が60点の配点、それ以外の法律科目が各30点の配点です。
民法・商法・民事訴訟法の試験時間が90分、憲法・行政法が60分、刑法・刑事訴訟法が60分、一般教養が90分と問題量の対して少なめの試験時間となっています。
一般教養は理系から人文科学の知識まで幅広く問われ、難易度も高めです。
タイトな試験時間なのでスピーディーに処理していく必要があります。
【論文式試験】
論文式試験は、長文の問題文を読み1500字程度の回答をします。
試験科目は、憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法・法律実務基礎目民事・法律時通基礎科目刑事・一般教養の10科目です。
憲法・行政法が140分、民法・商法・民事訴訟法が210分、刑法・刑事訴訟法が140分、法律実務基礎科目(民事・刑事)が180分、一般教養が60分の試験時間です。
配点は各50点の配点で500点満点です。
短答式と同様、試験時間には余裕がないため全て回答するために時間配分に気を配る必要があります。
【口述試験】
口述試験は面接試験のことで、試験時間は定められていません。
法律実務基礎科目(民事)と法律実務基礎科目(刑事)の2科目で60点が基準点とされています。
この試験は前者2つの試験とは異なり、合格させることを前提とした試験なので合格率も高くなっています。
★☆★ 予備試験に合格するための戦略 ★☆★

【短答式試験に効果的な対策】
短答式試験に効果的な対策は、過去問を解くことです。
この時、あらゆる知識をつけるためにも予備試験の過去問だけでなく司法試験過去問もあわせて解いてください。
過去問は数回解いただけでは終わらせず、確実に知識を覚えこむまで何度も繰り返すことが大切です。
同時に細かい知識がまとまっているテキストを読み込んだり、予備校の講座を受講するなどして知識を定着させましょう。
この際、条文もしっかりと意識しながら勉強することが重要です。
こうした学習を継続的に行い、しっかりと知識を身に着けることができれば、必ず合格できる試験です。
【論文試験に効果的な対策】
論文試験は基礎知識が中心に出題されますが、決して易しいものではありません。
かなり高い正確性が求められるので、テキストを読み込むなどして、正確な知識を身に着ける努力が必要です。
論文の試験なので記述の練習も忘れずに繰り返してください。
実際の試験を想定して毎日答案作成を行いましょう。
少なくとも1日1通は時間を計って答案をつくり、記述に慣れるようにしましょう。
【口述試験に効果的な対策】
口述試験は、法律実務基礎科目の内容を中心に民事・刑事の知識が身についていれば問題なく合格できる試験です。
論文式試験で勉強した内容がしっかり頭にはいっていれば十分なので、あまり心配せず面接にのぞんでください。
面接形式に不慣れで心配な場合は、予備校などで模試を受けるなどの対策をたてて口述試験の形式に慣れるようにしましょう。
予備試験の問題は基礎的な事柄を問われるものが多い反面、かなりの正確性が求められます。
あやふやな知識や理解不足では到底合格することはできませんので、徹底して過去問を解き、テキストを理解することに努めてください。
日々の繰り返しが合格への最短の近道です。
★☆★ 予備試験対策のお勧め予備校…アガルートアカデミーについて ★☆★

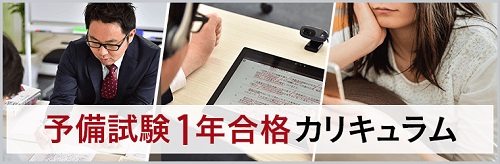
アガルートアカデミーは2015年1月に開校した資格の予備校です。
オンライン講義の配信を中心とした予備校で、受験生が本当に必要としている情報だけを提供しています。
予備試験の講座も充実しており、学習未経験者から学習経験のある中・上級者向けの講座や個別指導も実施しています。
受験生に必要なものだけを集めた合理的なカリキュラムは、予備校のスタッフが何度も協議を重ねて制作されたものです。
これらは、予備試験を徹底的に研究して制作されており、試験の合格のために必要な講座を組み合わせています。
総合的な対策・論文対策・過去問対策・短答式の対策など、本当に必要なものだけを提供して最短距離での合格を目指します。
通学スタイルの予備校と異なり、アガルートアカデミーではオンラインで講座を受講するため、いつでも、どこでも、自分のペースで講義を受講することができます。
また、何度も繰り返して視聴できるため、わかりにくかった部分をもう一度聞きかえして確認することも可能です。
ひとつのチャプターあたり10分から20分程度の構成になっているので集中しやすく、ぼんやりしているうちに講義が進んでしまったなどということがありません。
7段階の倍速機能やテキストの同時表示、音声ダウンロードなど予備校生が必要としている対策が万全に整っていることも大きな特徴です。
予備校に通いたいけれど、仕事をしていて時間がない方などにとってアガルートアカデミーのようなオンラインで学ぶことのできる予備校は、無理なく勉強できるというメリットがあります。
通常の予備校のように直接講師から指導を受けられなくて不安だという方がいるかもしれませんが、この予備校では、講師による毎月1回のカウンセリングが行われます。
学習状況についてアドバイス等をしてくれるので、不安な点など講師に質問することも可能です。
予備試験のための予備校を探しているが通学時間がないという方は、アガルートアカデミーのような通信制の予備校を検討してみると良いでしょう。
![]() 難関資格試験の通信講座【アガルートアカデミー】公式サイトはコチラ
難関資格試験の通信講座【アガルートアカデミー】公式サイトはコチラ
![]()
- アガルートアカデミーで後悔しないための情報《口コミでの評判を検証》のTOPページ
- 司法試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 行政書士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 公務員試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 宅地建物取引士試験(宅建試験)の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 社会保険労務士試験(社労士試験)の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 司法書士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- アクチュアリー試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 弁理士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 土地家屋調査士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 測量士補試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- マンション管理士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 中小企業診断士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 特定商取引法に基づく表記
