
こんにちは、最新の “お役立ち情報” をお届けする[Recommend Style]の横山です。
このページでは弁理士の基礎知識化から始まって、弁理士試験対策として評価が高いお勧めの予備校!
……アガルートアカデミーをご紹介させて頂きます。
弁理士試験の予備校に興味をお持ちの方は、どうぞ参考にしてください。
★☆★ 弁理士とは ★☆★
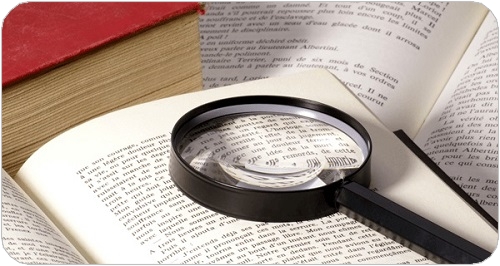
弁理士は、産業財産権に関するすべての手続きを業務として代理することができる、国家資格です。
弁理士は発明や考案、意匠や商標の出願や審判請求手続きを代理して、特許庁に登録し、権利を維持することを行います。
知的財産の存在感が世界規模で増しており、従来の特許の概念にとどまらず、世界中で高度化し、複雑化していることから、弁理士の資格も注目を集めるようになってきています。
知的財産は国内だけではなく、世界中に流通するため、弁理士は国際的な活躍が期待される職業になりました。
国内の企業が海外での特許を求めるだけでなく、世界中の企業が日本の特許を取得するときにも、弁理士が活躍しています。
大学や研究機関などにおける研究成果や開発された技術、商品や素材など、様々な物が取り扱われており、専任の部署を設けて対応しています。
また大企業やベンチャー企業なども、特許を専門にする部署を設けるようになってきているため、特許事務所への勤務や、特許事務所の経営の他にも、企業や研究所、大学に所属して活躍する弁理士が増えてきているというのが現状です。
インターネットが発達し、パソコンやタブレット、スマートフォンなどを使って世界中の情報を得ることが当たり前になっているのが現代社会です。
弁理士がコンテンツをプロデュースし、著作権の管理業務や収益構造の構築などを行うようになってきました。
従来の日本の弁理士に対する感覚よりも、もっともっと広い範囲で弁理士が活躍する場面が増えてきているため、注目されるようになってきており、必要度も高まっているのです。
資格と能力を生かして代理業務だけでなく、プロデュース業務もするようになることは、日本が国際社会で活躍するためには欠かせないことで、質が高い人材が求められています。
今まで裏方的存在だった弁理士ですが、これからの時代は、表舞台に立って仕事をバリバリこなす時代になっていくことでしょう。
★☆★ 弁理士の業務 ★☆★

弁理士の業務は知的財産にかかわることで、高い専門性が必要になります。
発明や考案、意匠や商標などを十分に保護するために、特許庁に出願をするという手続きを代理するということが、弁理士の主な仕事です。
またライセンス契約や、審決取消訴訟、侵害訴訟において、代理人となる業務も重要になってきています。
出願の依頼を受けた弁理士は、出願前の調査や出願、登録などの手続きを代行します。
依頼された内容について、先に出願や登録がされていないかなどを確認し、権利が取得できると判断した場合に、出願の代理を行うという流れです。
出願する場合には、願書の作成や発明等の内容を説明する明細書、デザインなどの衣装図面など出願に必要な書類を不備なく作成します。
審査を受ける場合には、特許庁の審査官とやり取りをする必要がある場合が多く、それも弁理士の業務になります。
近年では、弁理士は知的財産のエキスパートとして、技術的知識と法的知識を駆使して知的財産にかかわる幅広いコンサルティング業務を提供するようになってきています。
先端技術を保護し、利益を得るために、企業の知的財産保護は大変重要な意味を持ち、弁理士の需要が高まってます。
また競合他社が持っている権利に対する無効審判や、長期間使用されていない商標の不使用取消審判も、弁理士が代理することになります。
特許権侵害された場合には、弁護士と共同で訴訟の代理人となることも可能なのです。
このように弁理のは業務内容は幅広く、法律の知識が必要なだけでなく、コミュニケーション能力や、事務処理能力、訴訟にも対応できる能力などを兼ね備えていることが適応条件となります。
それらの能力に自信をもっているのであれば、学部や年齢、性別に関係なく資格を取得することができますので、どんどんチャレンジしてほしいと思います。
また最近では、公認会計士や行政書士などの資格を持っている人が、ステップアップのために取得するケースも増えてきているいう、注目の資格なのです。
★☆★ 弁理士のルーツ ★☆★

弁理士は、特許関係の取得に関わる業務をすることができる国家資格ですが、日本で初めて特許という考え方を広めたのは福沢諭吉です。
1867年に発表した西洋事情外編で制度を紹介したことが、特許のルーツとなっています。
そして、日本で特許制度の前身となるものが制定されたのが1877年で、明治政府が専売略規則を制定しましたが、特許制度についての考え方が広まっていなかったために、出願はありませんでした。
その後1877年に行われた第1回内国勧業博覧下で、最優秀賞を受賞した紡績機械が大変優れていることから、模造品が多数製造されたことが問題となり、1884年に商標条例ができ、1885年に専売特許条例が施行されました。
権利を守ることができる一方で、特許の申請をすることは大変難しく、専門家に代行してもらうようになったことが弁理士のルーツです。
1890年には特許局事務官が特許を代行する会社を神田と築地に開設し、現在の弁理士のような仕事をするようになりました。
1909年になり、日本に弁理士という制度が誕生し、特許法で特許弁理士以外が代理を行うことに罰則規定が追加されました。
現代の弁理士は、国家試験に合格した者だけがなることができる資格となっており、国家試験合格後は実務修習を修了する必要があります。
法律に関する知識が必要で、難易度も高い試験ですが、需要が高く、非常にやりがいもある仕事なので弁理士資格を取得したいという人は、特にここ数年、増加傾向にあります。
企業などの権利を守り、利益に貢献することができるだけでなく、日本の技術や商品、意匠などを幅広く守ることができる意識の高さが必要になります。
★☆★ 弁理士になるには ★☆★

弁理士になるためには、国家資格を取得することが必要で、その方法は3種類あります。
1.弁理士試験を受けて合格する方法が一般的で、短答式と論文式、口述式の3段階の試験を受け、すべてに合格することで弁理士資格を取得することができます。
2.司法試験を受けて、弁護士資格を取得することでも弁理士資格も取得することができます。
3.特許庁に就職し、審査官や審判官として7年以上の実務経験を積むことでも、弁理士資格を取得することができますが、弁護士資格を取得したり、特許庁に就職して実務経験を積むことは大変難しいため、弁理士を目指す人の多くが国家試験を受けるというのが現状です。
弁理士の国家試験に合格し、弁理士資格を取得してもすぐに業務を行うことができるわけではありません。
資格を取得してから実務修習を受講することが義務付けられているため、試験に合格した後には、特許事務所に就職して、実務経験を積むことが一般的です。
実務修習のカリキュラムを修了し、弁理士会に資格を登録することで、初めて業務を行うことができるようになります。
弁理士の国家試験は、1回の受験で合格する人は少なく、3回~4回程度の受けてから合格することが一般的です。
とても難しいため、独学で勉強するよりも専門の予備校を利用して、効果的に効率よく勉強をする人が多い傾向があります。
大学や大学院に通いながら予備校に通ったり、特許事務所に勤めながら予備校に通ったりするひとも多く、試験を突破するためには、効率の良い学習と努力の両方が必要になります。
★☆★ 弁理士試験の情報 ★☆★

弁理士試験は、弁理士になることを希望する人が業務に必要な学識と応用能力を有していることを判定するための試験です。
弁理士試験に合格し、実務修習を修了した場合に、弁理士となる資格が与えられます。
短答式と論文式の筆記試験及び口述試験を行い、短答式に合格しなければ、論文式を受験することができません。
例年3月中旬から4月上旬に願書の提出が行われ、受験票の発送は5月上旬ごろとなります。
短答式の筆記試験は、東京と大阪、名古屋に加え仙台と福岡でも行われ、時期は5月中旬から下旬です。
短答式筆記試験に合格することで、次の論文式筆記試験に進むことができます。
短答式の筆記試験の合格発表が6月上旬に行われてから、6月下旬から7月上旬に論文式筆記試験が東京と大阪であります。
論文式は、必須科目と選択科目の両方が行われますが、受験は片方のみでも可能となっています。
必須科目と選択科目の両方に合格することによって、次の口述試験を受験することができるシステムです。
短答式と論文式の両方に合格した場合にのみ、10月に行われる口述試験を受験することができます。
口述試験は、東京で行われ、合格発表は10月下旬から11月上旬ころに例年行われています。
具体的な試験期日については、毎年1月に官報で公告され、試験会場は毎年4月頃に官報と特許庁のホームページに掲載されるので、確認することが必要です。
学歴や年齢、国籍や性別などによる制限は一切なく、誰でも弁理士試験に挑戦することが可能です。
受験の手数料は、特許印紙で12,000円となっており、収入印紙と間違えることが無いように注意が必要です。
予備校では、毎年最新の試験情報を集めているので、官報だけでなく予備校でも情報収集が可能となっています。
★☆★ 弁理士試験に合格するための戦略 ★☆★

弁理士試験は出題科目が多く、試験範囲も大変広くなっています。 条文や判例、審査基準などいろいろな範囲からの出題がされるため、試験問題を分析することが必要になります。
試験範囲に含まれている知識を正確に把握、理解することが必要ですが、必要な知識量が膨大なので、効率よく学習し、定着させることがとても重要です。
合格するための戦略としておすすめなのが、予備校の活用です。
弁理士試験を専門としている予備校は、過去の問題を分析し、出題範囲や出題傾向などを反映させたテキストを作成し、効率よくポイントを学ぶことができるような講義を行っています。
弁理士試験では、法律や条文、判例など専門的な知識が多く、専門用語も多いので、予備校のテキストや講義で難しい専門用語や法律を覚えるだけでなく、理解することが効率よく学習することにつながります。
弁理士試験は大変難易度が高く、年々にもわたって挑戦している人もたくさんいますが、1年や2年の短期で合格している人もいます。
1年での合格を目指す人は、短答式試験と、論文式試験の両方を合格レベルまで並行して勉強することが必要になります。
早く勉強に取り掛かり、膨大な知識を吸収することになるため、無駄な勉強が省かれており、必要な知識が集約されている予備校のテキストと講義を徹底的に活用しましょう。
2年での合格を目指すなら、1年目は短答式試験の合格を目指して確実に勉強を進め、短答式試験の免除制度を利用して2年目に論文式と口述試験の合格を目指すという方法もあります。
2年での計画的な勉強が必要であり、仕事や家事、学業と並行して学習することは、2年をかけると言っても簡単ではありません。
弁理士の予備校を活用して、確実に合格ラインを突破することをお勧めします。
★☆★ 弁理士試験対策のお勧め予備校…アガルートアカデミーについて ★☆★

司法試験に次ぐほどの難関と言われている弁理士になるためには、国家試験を受験する必要があり、必要な知識は大変膨大です。
独学で合格する人や弁護士資格を取得する人、特許庁で実務経験を積む人もいますが、弁理士の予備校として大変実績が高いアガルートアカデミーを私はお勧めしています。
アガルートアカデミーで講義を行っている講師は、弁理士試験についての知識や、過去に出題された問題の分析力、受験生が陥りやすいつまずき、さらにポイントなどについて非常に精通している専門家です。
知識だけでなく、過去の問題から最新情報までを詳しく分析し、難しい知識であっても分かりやすく教える技術にも優れています。
さらにアガルートアカデミーが予備校として優れているのは、講師が作成したオリジナルテキストを使用しているところにあります。
試験の出題傾向をを徹底的に分析したテキストは、講義を行う講師自ら作成しています。
ですので、講義内容も非常にわかりやすく伝わるような配慮がなされているのです。
講義はインターネットで視聴することができ、板書やテキストへの書き込みなども駆使して行われるため、難しい法律用語や数的処理の複雑なとき方なども視覚的に分かりやすく、効果的に身につけることができることでしょう。
またアガルートアカデミーの講義は、予備校に通うことなくスマートフォンやタブレット、パソコンなどで視聴できるため、いつでもどこでも勉強をすることができます。
予備校へ通うことが大変な人や、時間的に合わない人、仕事や家事が忙しい人などでも予備校レベルの学習を、好きな時間に好きな場所でできるのです。
効果的に繰り返し学ぶことができる倍速再生やテキストの同時表示、音声ダウンロードなど、受講生が学習しやすい機能の充実は言うまでもありません。
このように最高品質の講義でありながら、比較的安い価格で受講できることも、アガルートアカデミーの魅力のひとつとなっています。
![]() 難関資格試験の通信講座【アガルートアカデミー】公式サイトはコチラ
難関資格試験の通信講座【アガルートアカデミー】公式サイトはコチラ
![]()
- アガルートアカデミーで後悔しないための情報《口コミでの評判を検証》のTOPページ
- 司法試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 予備試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 行政書士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 公務員試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 宅地建物取引士試験(宅建試験)の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 社会保険労務士試験(社労士試験)の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 司法書士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- アクチュアリー試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 土地家屋調査士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 測量士補試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- マンション管理士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 中小企業診断士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 特定商取引法に基づく表記
