
こんにちは、最新の “お役立ち情報” をお届けする[Recommend Style]の横山です。
このページでは司法試験の基礎知識化から始まって、司法試験対策として評価が高いお勧めの予備校!
……アガルートアカデミーをご紹介させて頂きます。
司法試験の予備校に興味をお持ちの方は、どうぞ参考にしてください。
★☆★ 司法試験とは ★☆★
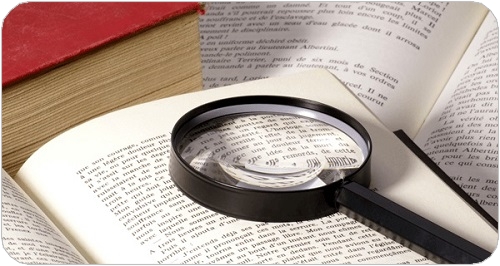
弁護士や裁判官、検察官になるためには、司法試験に合格する必要があります。
弁護士と裁判官、検察官は総称して法曹三者と呼ばれており、高いスキルと幅広く深い知識が必要なので、法曹三者に必要とされる学識やスキルを備えていることを判定するのが司法試験です。
司法試験は毎年1回開催されている試験で、短答式試験と論文式試験があり、4日間にわたって行われます。
憲法や民法、刑法をはじめ、幅広く専門的な分野からの出題になっており、難易度が極めて高い試験です。
大学で専門の勉強をしているだけで合格できるようなレベルでは無く、独学に加えて、さらに予備校も利用する人も多いです。
司法試験は、一度の受験で合格する人もいますが、2~3回の受験をする人が多く、中には10年以上かけ、やっと合格にたどり着く人もいるほどです。
難易度が高くて合格率が低い、超難関の国家資格となっています。
司法試験に合格した場合には、最高裁判所の下に位置付けられている司法研修所に採用され、1年間の研修を受けたのち、修了試験に2回合格すると、晴れて法曹三者になることができます。
司法試験を受けた後に研修を受けるだけではなく、司法試験を受験するためにも予備試験を受けることになります。
司法試験の受験資格は、予備試験に合格することと、法科大学院を修了することのどちらかを満たすことが必要という訳です。
法科大学院を修了していなくても、司法試験を受けることができる能力があることを証明する予備試験を受けると、司法試験の受験が可能です。
予備試験には受験資格がないので、誰でも受験することができます。
予備試験は、司法試験と同様に難易度が大変高いので、会社員や主婦などが受験する場合には、予備校に通うなどして高いレベルの勉強をする必要があります。
★☆★ 法曹三者(裁判官,検察官,弁護士)の業務 ★☆★

弁護士や検察官、裁判官の法曹三者は、日本の法秩序を守るという重要な役割を果たすことが業務です。
【弁護士】
弁護士は、法曹三者の中でも業務が広範囲にわたる仕事で、トラブルの解決にむけて代理人として裁判の中で弁護や主張をしたり、予測される事態に備えて適切な助言や予防策の提言など、社会に密着した仕事をすることが特徴です。
最近では、IT技術の発展によって、新しいビジネスモデルやサービスが次々と登場しており、新しいビジネスの法的リスクを検討したり、契約書の作成や交渉など業務範囲が広がってきています。
法律のプロフェッショナルとして、社会の動きを読み取り、正確に判断する能力が求められます。
【検察官】
検察官は、警察が捜査した事件を受理し、被疑者が犯人かどうかを確かめて起訴するかどうかを判断するという業務です。
事件を正確に把握し、人間の真意を見抜き、起訴が相当かどうかを判断していくため、幅広い知見と優れた能力が必要で、責任とやりがいの大きな仕事になります。
被害者と被疑者の両方と直接接点を持ち、両者の主張を生で聞き取り、正当な判断をしていきます。
ドラマなどでも取り上げられることが多く、世間からの関心も高い分、職責も大きいといえます。
【裁判官】
裁判官は、裁判において最終的な判断を判決という形で下していくことが業務です。
民事裁判であれば双方の当事者の主張を聞き、刑事裁判の場合は検察官と弁護人の主張を聞いて法律をもとに判決を下すという判断をします。
大きな責任を伴い、後の裁判にも影響を与える仕事なので、法的知識や判例の知識はもちろん、判断力や人間性など幅広い能力とスキル、知識が兼ね備えられている必要があります。
責任が大きいだけでなく、世間からの関心や意見も多いのですが、やりがいのある仕事とも言えます。
★☆★ 司法試験のルーツ ★☆★

日本の法曹という職業は、1870年代から1880年代に日本の近代国家に不可欠な制度として、西洋から導入されたことがルーツとなっています。
そして1890年に開始された弁護士試験が、現在の司法試験の始まりです。
国家的に重要な職種である法曹制度が始まり、1891年には、現在の裁判官と検察官にあたる判事と検事を採用するための判事検事登用試験が始まりました。
その後1922年に、弁護士試験と判事検事登用試験が統合され、高等文官試験司法科が実施され、この試験が現在の司法試験へとつながっています。
さらに戦後、日本国憲法の施行に伴い、司法制度の変革が行われ、1949年に司法試験が開始されました。
1949年に開始された司法試験は、現在では旧司法試験と呼ばれており、学歴不問で誰でも受けることができる反面、最終合格率は1~3%の狭き門で、日本一難しい試験というイメージができました。
弁護士試験を受けるための資格や条件はなく、学歴不問となっていましたが、判事検事登用試験は司法省指定学校卒業者等だけが受験できることになっていました。
検察官や裁判官になる方が、資格的なハードルが高かったのです。
1999年以降になると司法制度改革が推進され、2004年に法科大学院が設置されました。
法科大学院は専門職大学院で、修了することで、司法試験の受験資格を得ることができるようになります。
現在では、法科大学院を修了しているか、予備試験に合格しているかのどちらかの方法で、司法試験の受験資格を得ることができるというシステムとなっています。
現代においても司法試験は難関ですが、歴史的にみてもハードルは大変高く、知識と能力を兼ね備えており、努力も必要であったことが分かります。
★☆★ 法曹三者(裁判官,検察官,弁護士)になるには ★☆★

裁判官や検察官、弁護士の法曹三者になるためには、司法試験に合格しなければなりません。
司法試験、誰でもいつでも受験をすることができるという試験ではなく、一定の受験資格が必要になります。
受験資格を得るためには、大きく分けて2つのルートがあり、どちらかのルートをたどることになります。
2つのルートは、
・法科大学院に進学し、修了する法科大学院ルート
・司法試験予備試験に合格するルート
になります。
どちらを選んでも、最後に受験する司法試験は同じです。
【法科大学院で受験資格を得るルート】
法科大学院で受験資格を得るルートは、時間的、経済的負担は大きいですが、確実性もその分高いと言われています。
法科大学院へ進学するためには、4年制大学を卒業していることが必要であり、法科大学院の学費として総額で300万円~500万円が必要になります。
奨学金制度を設けている大学院もありますが、経済的な負担は高いと言えるでしょう。
大学入学から司法試験の受験資格を得るまでには、法学既修者が6年、法学未修者だと7年の歳月がかかります。
【予備試験を受けるルート】
予備試験を受けるルートは、予備試験自体が司法試験と同じくらい難しい試験になっています。
時間的、経済的負担が少なく、学歴や年齢の制限がないので会社員や主婦などでも合格を目指すことができます。
難関試験のために予備校を利用する人が多く、書籍代や学費が50万円~程かかりますが、合格までの期間や経済的な負担の総額は、個人差によって大きく異なります。
予備試験はハイレベルな法律の知識が必要で、司法試験と同じくらい難しい難関試験となっとおり、予備試験の合格までに時間が掛かる可能性はありますが、最短では学習開始から2年程度で司法試験の受験資格を得ることが可能です。
★☆★ 司法試験の試験情報 ★☆★

司法試験は、毎年5月に実施される法曹三者になるために必要な学識と応用能力を有することを判定するための試験です。
司法試験を受験することで、国民の権利を守るために憲法や法律に基づき、
・公正な裁判を行う仕事をする裁判官
・犯罪を捜査し、犯人に対して裁判を起こす仕事をする検察官
・事件や紛争について法律の専門家として適切な予防方法や対処方法、解決策をアドバイスする仕事をする弁護士
になることができます。
司法試験には、短答式試験と論文式試験があり、両方の試験を受ける必要があります。
短答式試験で一定の点数を取ることができた人が、論文式試験の採点対象になり、最終的には短答式と論文式の比重が1対8になるように調整したうえで合計点を算出し、合否が決められることになっています。
司法試験は例年5月に行われており、短答式は憲法と民法、刑法から出題されます。
論文式は、憲法や行政法、民法などの必須問題と、倒産法や租税法、経済法などの選択科目から1科目が出題範囲です。
司法試験の合格率は、実際に受験した人のうち、例年20%強で推移しており、短答式試験の合格率は65%強、論文式試験に進んだ者の合格率は30%強という内訳です。
非常に難関であるというイメージがありますが、他の国家試験では、合格率が一桁というものもあるので、予備校などに通って努力をすることで、合格する可能性がでてくる試験だということが言えます。
司法試験の受験には資格が必要で、4年制の大学を卒業したのちに法科大学院を修了するか予備試験に合格するかのどちらかのルートをたどることが必須です。
★☆★ 司法試験に合格するための戦略 ★☆★

専門的で幅広い法律的な知識と、法律のプロフェッショナルとしてのスキルが試される司法試験に合格するためには、膨大な量の勉強を、効率よく、しかも確実に行う必要があります。
独学で合格をしたり、法科大学院で学んだりすることもできますが、効率性と確実性を重視して学習をしたい場合には、司法試験を専門としている予備校を活用することが、合格するための戦略と言えるでしょう。
司法試験は、勉強を開始してから数か月で合格ラインに達することはほとんど無いくらいの知識量が必要な試験です。
相当な努力をしても最低で1年以上はかかるため、学習開始から2年程度の期間で受験を目指すのが最短ルートと言えます。
予備試験を受験する場合には、予備試験の受験と合格の後、司法試験を受けることになりますので、最短で3年前後の準備期間が必要です。
市販のテキストや六法全書などを駆使して勉強をすることも可能ですが、短期合格を目指すなら、予備校のテキストを使用し、講義を受けることをおすすめします。
専門にしてる予備校のテキストや講義であれば、司法試験を分析し、研究し尽くしているので、必要な知識を落とさず、効率よく学ぶためのカリキュラムが組まれているので、集中して学ぶことができます。
とにかく司法試験の勉強は、とても優秀な人でも、試験対策に数年の期間を要します。
学習方法が効率的であり、記憶に残りやすい方法で、繰り返し勉強を重ねることを戦略的に行う必要があります。
予備試験と司法試験の合格者の中には、法律系の大学出身者ではない普通の会社員や、主婦なども現実に存在しています。
予備校で学習しながら、仕事や家事と試験対策を両立して合格することができている人もいるのも現実なので、効率の良い学習方法を取り入れることで、一般の人でも合格することが可能ということになります。
★☆★ 司法試験対策のお勧め予備校…アガルートアカデミーについて ★☆★


司法試験に合格することを目指す予備校として、私はアガルートアカデミーをおすすめします。
アガルートアカデミーで講義や個別指導を担当する予備校講師は、全員が実際に合格しているプロの予備校講師なので、具体的なアドバイスを受けたり、勉強法を教えてもらうことができます。
もちろん講師が全員司法試験に合格しているだけでなく、受験指導の経験も豊富です。
法的な知識を持っているだけでなく、司法試験を受験するにあたって、ポイントや出題傾向などについての知識と経験に加え、豊富な指導力を誇っているのです。
アガルートアカデミーで使用するテキストは、合格に必要な知識を集めるだけでなく、信頼できる文献の裏付けもとった上で編集がなされています。
何度も繰り返し学習に使用する基幹講座のテキストは、資格的にわかりやすいフルカラーとなっており、効率よく受験対策をすることができるでしょう。
またアガルートアカデミーでは、いつでもどこでも効率よく学習ができるように、インターネット環境があればスマートフォンやタブレット、パソコンで講義を視聴することができます。
最大3倍までの倍速再生が可能で、テキスト同時表示や音声ダウンロードなど、時間を有効に活用できるような工夫がされている多機能な受講システムを採用しているのです。
基本的にアガルートアカデミーは、通信講座をメインとする予備校ではありますが、難関試験を突破するために、個別指導や個別フォローにも力を入れています。
プロ講師による手厚いサポートやフォローを受けることができることも、司法試験を受ける人にアガルートアカデミーをおすすめする理由のひとつです。
![]() 難関資格試験の通信講座【アガルートアカデミー】公式サイトはコチラ
難関資格試験の通信講座【アガルートアカデミー】公式サイトはコチラ
![]()
- アガルートアカデミーで後悔しないための情報《口コミでの評判を検証》のTOPページ
- 予備試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 行政書士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 公務員試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 宅地建物取引士試験(宅建試験)の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 社会保険労務士試験(社労士試験)の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 司法書士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- アクチュアリー試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 弁理士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 土地家屋調査士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 測量士補試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- マンション管理士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 中小企業診断士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 特定商取引法に基づく表記
