
こんにちは、最新の “お役立ち情報” をお届けする[Recommend Style]の横山です。
このページでは土地家屋調査士の基礎知識化から始まって、土地家屋調査士試験対策として評価が高いお勧めの予備校!
……アガルートアカデミーをご紹介させて頂きます。
土地家屋調査士試験の予備校に興味をお持ちの方は、どうぞ参考にしてください。
★☆★ 土地家屋調査士とは ★☆★
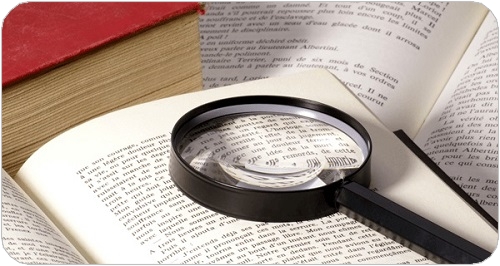
あまり不断の生活ではなじみがないかもしれませんが、代表的な国家資格のひとつに土地家屋調査士という専門職があります。
土地家屋調査士の意義を確認しておくと、不動産の表示に関する登記について、土地や建物に関する調査や測量を行い、法務局に新生する表示登記に代理を行う専門家のことです。
そもそも法務局に備えられている登記簿謄本には、「表示の登記」と「権利の登記」の二種類が記載されています。
このうち「表示の登記」には、土地や建物の面積や地積・建物の構造や用途、各階の面積など、不動産の物理的状況が記載されています。
一方「権利の登記」では、不動産の所有者や担保権など、各種の権利の設定や、移転・変更や移転など、権利の変遷が記載されている訳です。
相続などで名義を移転するのは「権利の登記」に該当するので、代理を依頼するのは司法書士という専門職になります。
土地の面積や地目、建物の新地区やリフォームなどで不動産の物理的現況変更があったときに、調査や測量を行い、申請代理などを専門にするのが、土地家屋調査士になります。
建物や土地の所有者は、表示に関する事項について変更があったり、誤りがあっ多場合には、二週間以内に必要な表示変更登記を申請する義務を負っています。
この申請義務を怠ると、過料という金銭支払を伴う行政処分を受けるとされていますが、事実上空文化しているので、誰も申請義務を意識することはありません。
その結果として、土地家屋調査士の知名度が高くない理由のようです。
しかし、実際には戸建て住宅を購入するなどの時には、必ず土地家屋調査士が表示登記を行うことで、はじめて買主の登記名義をのせることが可能になるので、重要な役割を担っている専門職の一つです。
それゆえ1件当たりの報酬が比較的高いのも、土地家屋調査士の魅力と言えます。
★☆★ 土地家屋調査士の業務 ★☆★

土地家屋調査士は、土地や建物の表示に関する事項の調査や測量を行い、法務局へ申請する表示登記の申請代理をするのが主要な業務です。
「表示の登記」には、土地や建物の物理的状況を反映させたデータが記載されており、変更が起きたり誤りが発覚したときには、原状と登記簿の不一致を是正するべく、必要な登記を申請する義務を負っています。
しかし建物と土地とでは、かなり内容は異なります。
そこでマイホームなどで販売されていることが多い、建売住宅を事例に土地家屋調査士の業務をご紹介しましょう。
建売住宅は、数棟からそれ以上の数の新築住宅を、特定のエリアで建築して売りだすのが一般的です。
時には数千平米以上の広い敷地を、ここの住宅が建築できるようにするため、境界を区切って販売する住宅の数に応じて分ける必要があります。
これが分筆登記とよばれるもので、土地家屋調査士の主要な業務の一つです。
具体的には法務局や市役所などで事前調査を行い、その後は現場に足を運んで測量を行います。
測量を元に地積測量図を作成し、申請書とともに法務局に提出します。
さて、分筆登記が終了すれば、いよいよ住宅の建設が始まります。
内装以外の外壁など、建物の計上になった段階で、今度は建物表題登記を申請するために、建物の構造や面積などについて調査と測量を行い、建物図面や各階平面図といった図面を作成します。
この図面に建物表題登記申請書を法務局に提出すると、登記簿が備えられることになるのです。
この表題登記は所有権や抵当権などの「権利の登記」の全体をなすもので、非常に重要になります。
買主の方は、建売住宅の場合少ないかもしれませんが、住宅ローンを組んで住宅を購入するときには、土地家屋調査士の仕事が必ず実践されています。
土地家屋調査士は、それほど大切な仕事というわけです。
★☆★ 土地家屋調査士のルーツ ★☆★

土地家屋調査士のルーツを探るには、かつて税務署で備え付けられていた「土地台帳」や「家屋台帳」にまで話しをさかのぼる必要があります。
現在では、土地や建物などの不動産の記録やデータは、管轄の法務局やサーバに保管・記録されていますが、戦後暫くの間では、税務署が管理していました。
当時は固定資産税は国税の一種であって、市場価値も配慮した課税額を算出する必要がありました。
そこで税務署では、専門の調査員を配属することで、土地や建物の現況を把握していたのです。
そしてそのデータを文書化したものが、土地台帳であり家屋台帳であったわけです。
ところが第二次世界大戦後の経済改革の一環で、固定資産税は国税から地方税に換わることになり、地方自治体へ財源委譲がされることになりました。
これが昭和24年に実施された占領当局の、「シャウプ勧告」に伴う税制改革の実施です。
その結果、これまで税務署で管理されてきた、土地台帳や家屋台帳を一元化することになり、課税目的の「台帳」から現況を正しく反映させる目的を実現するために、税務署の直轄から管轄法務局(登記所)に移管されます。
しかし、当時の法務局の職員には、税務署の調査員のような専門知識を習得している人材は非常に不足していたため、土地台帳や建物台帳の記録の取り扱いや、測量なども手探りで開始するような状況でした。
それによって不動産の表示に関する職業専門家の必要性が痛感されます。
そこで台帳業務の適正化や登記手続きの円滑化、並びに国民の不動産の権利を明確にすることを目的に、昭和25年7月31日に、土地家屋調査士法が制定されることになりました。
現在では土地の境界に関する争いがあるときに、認定土地家屋調査士に限り、弁護士と共同して裁判外紛争処理の代理人の業務を取り扱うことも認められています。
★☆★ 土地家屋調査士になるには ★☆★

土地家屋調査士の業務を専門職としてを行うには、事務所を設置しようとする調査士会に入会すると同時に、土地家屋調査士連合会の名簿に登録をすませることが必要です。
これが表示登記に関する独占的専門業務と呼ばれる所以ですが、そのためには登録されるための資格を取得することが前提となります。
ところで土地家屋調査士になるには、法務省の職員として、登記事務に携った経験をもとに、法務大臣の認定をうけるか、国家試験である土地家屋調査士試験に合格するかの、いずれかの方法をクリアすることが必要です。
法務省で登記業務に携わった経験など無いのが一般的なので、独学か予備校で勉強を重ね、土地家屋調査士試験に合格するのが普通のルートです。
土地家屋調査士試験は毎年1回実施されており、10月第三週に筆記試験が、翌年の1月第三週目に口述試験が実施されています。
ちなみに平成29年までは毎年8月に筆記試験が行われ、11月に口述試験が実施されていました。
この土地家屋調査士試験は、国家試験のなかでも一定の得点をクリアすれば合格できるスタイルではなく、合格基準点を突破して合格枠に滑り込む必要があるので、競争試験となっています。
口実試験はほぼ100%合格するので、筆記試験を合格できるかが事実上の天王山になります。
試験は正しい選択肢を選びだす択一問題(マークシート形式)と、申請書の一部を記載したり各種の図面を作成する記述式問題から構成されています。
それぞれには毎年合格基準点が設定され、基準点に到達しないかぎり、足切りされることになります。
しかも合格基準点を突破したうで、さらに合格圏内の得点をあげた他の受験生との競争に打ち勝つ必要があるので、ハードルはかなり高いものと考える必要があります。
★☆★ 土地家屋調査士試験の情報 ★☆★

土地家屋調査士試験には、特に受験資格は設定されていないので、誰でも受験することができます。
独学で挑む方もいらっしゃいますが、受験生活を早めに切り上げたいと考えるなら、専門の予備校を利用するのが賢明といえます。
その理由は、土地家屋調査士試験の独特の受験内容にあります。
土地家屋調査士試験は、午前の部と午後の部の二部構成になっています。
午前の部では土地建物に関する測量につき、択一式問題10問と記述式1問が出題されますが、ほとんど受験する方はいません。
なぜなら測量士補や測量士、建築士などの専門資格を取得していれば免除されるからです。
測量士や建築家になると、専門の教育を過程を受ける必要がありますが、測量士補は比較的難易度が低いので、受験生は測量士補試験に合格してから、土地家屋調査士試験を受験するのが一般的です。
したがって、午後の試験の筆記試験と、筆記試験合格者を対象に実施される口述試験に合格することが、土地家屋調査士になるためには、マストのタスクと言うことになります。
土地家屋調査士試験の受験科目は、民法や不動産表示の登記申請についての専門知識が対象になっており、主要科目は不動産登記法や、測量に関する専門知識、民法などになります。
筆記試験では建物図面や地積測量図の作成が必要です。
そのため通常の電卓だけでなく、プログラム機能や文字入力の機能を備えていない関数電卓などの持ち込みも可能です。
作図に際しては250や500のスケールの三角定規や三角スペース、コンパスなどの持ち込みも許可されています。
午後の筆記試験は選一式問題が20問、建物と土地に関する筆記試験が2問出題され、2時間30分で回答します。
とにかくスピードが命なので、専門予備校で入念な対策が必要になります。
★☆★ 土地家屋調査士試験に合格するための戦略 ★☆★

土地家屋調査士には、特に受験資格も設定されていませんが、専門性の高い知識が問われる競争試験なので、、合格のハードルは高いのが現実です。
最近の合格率は概ね9%弱で推移していますので、独学で短期間で合格をめざすのは困難と言えます。
しかも午前の部は難易度が高いので、まず測量士補試験の合格を実現することが必要です。
測量士補試験は測量に関する基礎的知識を対象に、28問出題され18問以上得点すれば合格できます。
競争試験ではないので、合格率も高い年では40%をこえることもありますが、土地家屋胃調査士試験対策に取り組むには、早く合格するのがポイントです。
測量に関する知識は高校の三角関数についての知識が要求されるので、特に文系出身者の方は、専門の予備校を利用するのが賢明です。
土地家屋調査士対策に測量士補試験対策もパックになっているコースがあるので、導入を検討してみることをお勧めします。
土地家屋調査士の口述試験はほぼ合格するので、筆記試験を突破するのが実質的な最終目標です。
択一式問題は教科書で読みすすめながら早めに過去問に挑戦して、出題傾向を把握すると同時に問題を解き、、また教科書に戻って知識を確認することがポイントになります。
そして土地家屋調査士試験の難関といえるのが、二門の記述式問題の攻略にあります。
関数電卓の利用法をマスターするのはもちろん、正確に早く作図することが求められます。
短時間の間に座標データを元に、基準点などを算出するのは、スピード感が求められます。
また地積測量図などを作成するには、三角定規やコンパス・分度器などを駆使した製図作成技術をマスターすることが必須です。
市販の教科書では、実際に書く作業に結びつけるのは難しいので、予備校の製図に焦点を当てた講座を利用するのが近道と言えるでしょう。
★☆★ 土地家屋調査士試験対策のお勧め予備校…アガルートアカデミーについて ★☆★

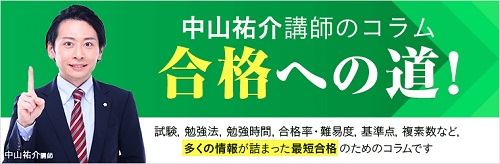
土地家屋調査士には特に受験資格がないので、年齢をとわず誰でも受験することが出来ます。
しかし、法律系の専門資格のなかでは、数学の素養が要求されるユニークさを持っています。
学生時代、文系出身の方では、とりわけ記述式問題がネックになり、挫折したり長期間の受験期間を余儀なくされることも珍しくありません。
できる限り、短期間での早期合格をめざすなら、土地家屋調査士試験対策にノウハウを持ち、さらに実績豊富な専門の予備校を利用するのが賢明です。
専門の予備校にはいくつかの選択肢がありますが、私がお勧めできる土地家屋調査士試験予備校はアガルートアケデミーになります。
なぜならアガルートアカデミーは、受験生のレベルに対応したカリキュラムを用意している予備校だからです。
例えば土地家屋調査士の合格を目標とするにしても、数学には苦手意識があり、図面を引く経験も皆無という方は珍しくありません。
法律系の科目の試験対策は何とかなる優秀な人でも、数学や製図はお手上げと言うのが、多数の受験生の姿といえるかもしれないのです。
アガルートアカデミーでは全く知識ゼロの人でも、測量士補と土地家屋調査士の両方の合格が可能なカリキュラムが用意されている予備校です。
土木系や技術系の職業の経験がある方では、測量士補や建築士などの資格をもつ方もいるでしょう。
アガルートアカデミー予備校では、このような午前試験免除者を対象に午後の部の筆記試験をケアするカリキュラムも用意されています。
また、土地家屋調査士試験予備校で勉強をすすめるうちに、疑問点がでることもしょっちゅうです。
アガルートアカデミー予備校では、facebook経由の質問や毎月1回の定期カウンセリングも利用できるようになっています。
このようにアガルートアカデミーは、土地家屋調査士試験対策としてのカリキュラムもフォローも、非常に充実した予備校と言えるのです。
![]() 難関資格試験の通信講座【アガルートアカデミー】公式サイトはコチラ
難関資格試験の通信講座【アガルートアカデミー】公式サイトはコチラ
![]()
- アガルートアカデミーで後悔しないための情報《口コミでの評判を検証》のTOPページ
- 司法試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 予備試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 行政書士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 公務員試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 宅地建物取引士試験(宅建試験)の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 社会保険労務士試験(社労士試験)の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 司法書士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- アクチュアリー試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 弁理士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 測量士補試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- マンション管理士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 中小企業診断士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 特定商取引法に基づく表記
