
こんにちは、最新の “お役立ち情報” をお届けする[Recommend Style]の横山です。
このページでは司法書士の基礎知識化から始まって、司法書士試験対策として評価が高いお勧めの予備校!
……アガルートアカデミーをご紹介させて頂きます。
司法書士試験の予備校に興味をお持ちの方は、どうぞ参考にしてください。
★☆★ 司法書士とは ★☆★
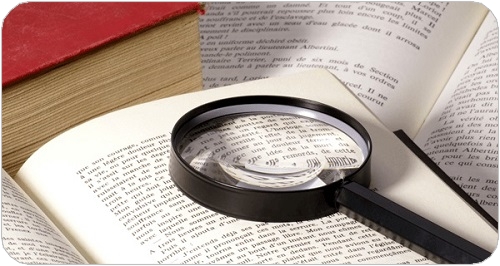
司法書士とは、いわゆる登記の申請代理を主な業務に取り扱う専門職のことを言います。
登記には、大別すると不動産と商業の二種類があり、
・不動産登記…土地や建物に関する権利状態を公的に記録する
・商業登記…会社や各種法人に関する事項を公的に記録する
になります。
登記とは、法務局備え付けのサーバーに権利移転の過程などを記録して、公的に権利関係を証明する仕組みのことです。
いわゆる登記簿謄本とは、法務局で登録されているデータを書面などに印刷し、登記官が公印を押印して第三者に権利関係などを証明したものです。
普段の生活のなかでは馴染みの薄い登記ですが、どうしてこのような公的照明手段が整備されているのでしょうか。
少なくとも日本国内では、すでに100年をこえる歴史があり、度重なる改正をへて現在のスタイルに収斂してきた経緯があります。
土地や建物などの不動産や、会社などの法人は、経済活動において重要な役割をになっており、財産的価値も高く評価されます。
価値が高いだけに、誰が権利者であったり、会社役員が誰であったりなどの権利関係が、誰でも確認できる制度が必要になります。
高いお金を工面して不動産を購入しても、誰に対しても、自分が所有権などの正当な権利に基づいて所有している事実を確定的に主張できる立場が保証されていない限り、安心して不動産などを購入しようとはしないはずです。
ところが経済的価値が高いからこそ、容易に記録が改ざんされるようでは、公的に権利関係を証明したところで、絵にかいた餅になってしまいます。
そこで、登記簿に権利関係を反映させ、法律に基づき厳格な手続きを備えることで、登記簿の信頼性を上げることにしたのです。
しかし、一般人では登記簿に権利関係を反映させるのは困難なため、専門職の司法書士が制定されたわけです。
★☆★ 司法書士の業務 ★☆★

不動産登記や商業登記の専門家である司法書士の業務は、案外多岐にわたっています。
一般の方が司法書士と顔を合わせる機会が多いのは、土地や建物などを購入する場面ではないでしょうか。
具体的に言えば、ローンの審査を通過して、住宅ローンも利用できることになり、売主に売買代金をはじめとした諸経費を支払う目途が付いたとします。
いわゆる決済を行うことで所有権を取得し、マイホームなどを手にすることが叶うことになります。
決済とは数千万円に及ぶこともある不動産の売買代金を、売主に支払い不動産物件の引渡しを行う手続きのことです。
その現場で重要なのは言うまでもなく、円滑に売買代金の振込みが完了することにありますが、それと同等に重要なのは、責任をもって登記名義を買主に移転させることです。
登記名義を移転すれば、売主は完全に所有権を喪失する一方で、買主は確定的に所有権を取得し、第三者に対しても権利を主張することが可能になります。
しかも対価として、巨額の現金が移動するので、価値中立的な立場で専門家が見届けることが重要です。
この決済現場を主導し無事終了まで導くのが、司法書士の主要な業務の一つになります。
決済現場では、支払の確認などだけでなく、所有権移転登記を申請するのに必要な書類に押印してもらって、法務局に必要な書類を提出するまでが司法書士のお仕事です。
住宅ローンも同時に設定するのであれば、金融機関から担保権設定登記に必要な書類のやり取りを行い、売買と同時に抵当権設定登記などを提出することもあります。
また裁判所に提出する書類の作成なども、古くより司法書士の業務と位置づけられてきましたが、平成14年ごろより、簡易裁判所に継続する訴訟の代理業務なども法律で認められるようになりました。
★☆★ 司法書士のルーツ ★☆★

司法書士は、司法書士法に基づき、
・不動産や商業登記の申請代理
・供託の代理
・裁判所や検察庁、公証人役場などに提出する書類の作成・提出
・財産管理業務
などを取り扱っています。
ただ現在の司法書士のスタイルの完成をみるまでには、いくかの変遷を経てきました。
司法書士のはじまりは、1872年の四方職務官制に基づく代書人制度に見ることが出来ます。
太政官布達により、証書人・代書人・代言人制度が制定されたわけです。
証書人は現在の公証人で、代言人は現在の弁護士に相当する職務です。
1886年には不動産登記法が制定され、現在の司法書士の職務の不動産登記や、商業登記の業務の基礎が形成されました。
実は不動産登記法は、憲法や民法よりも先に制定された法律です。
この制定を契機に、代書人はフランス型の訴訟だけに関与するスタイルから、英国型の法務や一般民事事件に関与する色合いが濃厚になったわけです。
1919年には司法代書人法が制定され、当時すでに行政代書を行っていた一般の行書人との職務の違いが明らかになります。
1935年には旧司法書士法が成立し、司法代書人から現在の司法書士へと名称も変更されました。
第二次大戦が終了し、新憲法が公布されると、現行の司法書士法が成立し、政府の全面的な監督制度も廃止されています。
1978年には国家試験が導入されて、現在の司法書士のスタイルが定着しました。
そして2002年になると、当時の司法制度改革の一環として、簡易裁判所での代理業務などが新たな職務に加わり、少額の民事事件では、素養代理人として活躍できる舞台が広がることになったのです。
しかし、簡易裁判所訴訟代理は従来の登記業務とは大きくスタイルがことなるので、認定司法書士制度が導入され現在に至っています。
★☆★ 司法書士になるには ★☆★

司法書士になるには、おおきくわけると3つのルートがあります。
まず司法試験に合格する方法…いわゆる法曹三種になるための登竜門である司法試験を突破すると、弁護士や判事だけでなく、司法書士や税理士などの専門職に付くことが出来ます。
ただし、わざわざ司法試験に合格して司法書士になるというのは、現実的な選択肢ではありません。
もっとも司法書士が、司法試験に合格して、弁護士事務所と兼業する事例はあるようです。
そこで現実的なのは、司法書士試験に合格するか、法務省に奉職し実務を経験し、司法書士の開業許可を法務省から得ることです。
となると、法務省職員でもない一般の方が、司法書士を目ざすうえで現実的な選択肢は、司法書士試験に合格することになります。
試験自体は非情にシンプルで、筆記試験と面接試験を通過すれば、めでたく合格の運びになります。
しかし、筆記試験は午前の部の2時間と、午後の部の3時間を一日でこなすことになります。
筆記試験を突破すると、都市部の法務局で実施される面接試験を突破することが必要です。
もっとも面接試験は、事実上ほぼ90%以上の確率で合格しますので、筆記試験合格が事実上の天王山になります。
受験資格には特に限定がなく、義務教育を終了していれば、男女生別も年齢も職歴も関係なく、誰でも受験することができます。
試験対策のための教科書も大型の書店であれば販売されているので、独学でも合格するのは可能でしょう。
しかし、受験科目は非情に専門性が高く、特に不動産登記胞や商業登記法などは、技術的で難解な部分が多くなるので、諸学者の方が独学で合格可能なレベルまで習得するのは難しいものがあります。
できるだけ早く合格して、受験生活を短くしたいのであれば、専門の予備校を利用するのが賢明です。
★☆★ 司法書士試験情報 ★☆★

司法書士試験は、筆記試験と面接試験がありますが、筆記試験を突破すれば、面接試験はほぼ受かるので、いかにして筆記試験を突破するかが最重要課題です。
筆記試験は午前の部の択一試験と、午後の部の記述四季問題を含めた試験を1日ですませることになります。
午前の部・午後の部、それぞれに合格基準点があり、一点でも合格基準に到達しない限り、足きり対象になり不合格となります。
合格基準点は「午前の択一試験」「午後の部の択一問題」、そして「記述式問題」のいずれにも設定されています。
すべての部門の設問の基準点をクリアして、初めて採点の対象になるわけです。
合格するためには、3つの関門をクリアし、さらに総合的な合格基準点を上回ることが求められます。
極端なことを言えば、午後の部で満点近くの答案が出来ても、午前の部の試験で1問獲得できず、合格基準点をクリアできなければ、不合格になるというわけです。
このような試験の特性を踏まえると、予備校を利用して事前に対策を済ませておくのが、受験生にとってはマストの作業になってきます。
ところで司法書士試験では、午前と午後で試験内容に大きな違いがあります。
午前では「憲法・民法・刑法」に「会社法・商法」が試験科目となり、マークシートで35問をそれぞれ正解を択ぶというスタイルです。
ちなみに試験時間は2時間となっています。
これに対して午後の部では、「35問の選一問題」と「2問の記述式」といった2問が出題され、3時間の間に答案を作成する必要があります。
選択肢を択ぶ問題では、民事訴訟法をはじめとして、民事執行法や不動産登記法、商業登記法などが出題されます。
そして記述式問題は、不動産登記法、商業登記法が1問ずつ出題され、実際に申請書の中身や添付書類、登録免許税など多彩な内容について、問題の指示通りに正解を見い出すことが求められます。
★☆★ 司法書士試験に合格するための戦略 ★☆★

司法書士試験の特徴のひとつに、試験科目が広範囲にわたる点を指摘することが出来ます。
業務の性質上、不動産登記法や商業登記法や民法、会社法などが出題範囲に含まれるのは当然です。
しかし、憲法や民事訴訟法、供託法など、あまり馴染みのない、専門的、技術的な法律科目も含みます。
さらに合格点レベルの受験生は、絶対に落とさない問題を、確実に得点してくるので、苦手意識を持っているようでは、合格はおぼつかないものと覚悟したほうが良さそうです。
受験生のなかには補助者をしながら、10年を超えて受験生活を送る人も珍しくありませんが、受験生の誰もが早期合格を望んでいるはずです。
そのために戦略的には、司法書士試験合格のための勉強を実践する必要があります。
まず留意するべきなのは、得意な科目だけで得点を重ねても、合格基準を突破するのは困難と言うことです。
逆にいえば、どの試験科目についても、満遍なく正解を導き出せることが重要ということになります。
そのためには、まず苦手科目を明らかにし、苦手な分野や難解な科目を潰していく姿勢が必須です。
概ね午前の部では8割以上の得点と、午後の部でも選択式の問題で8割以上の得点が合格ラインになります。
二時間と三時間の試験時間ときくと、けっこう長い試験との印象をもたれるかもしれません。 しかし、実際に試験に臨めば、むしろ時間切れに終わる受験生は決して珍しくないわけです。 特に記述式問題が出題される午後の部は、いかに早く選一問題をすませて、記述式問題のために時間を余らせることが出来るかが重要です。 このため、司法書士試験を効率的に合格するには、予備校を利用するのが得策となります。
司法書士試験対策の予備校では、それぞれの試験に対応した答案練習会が開催されます。
短期合格者のほとんどが、予備校利用者という現実があるのです。
★☆★ 司法書士試験のお勧め予備校…アガルートアカデミーについて ★☆★

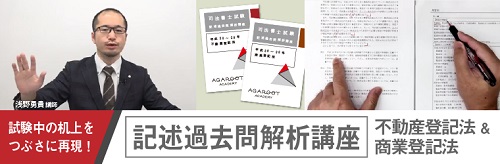
国家資格のなかには、一定の得点を獲得すると、全員合格という種類もあります。
しかし司法書士試験の場合、合格基準点を突破するだけでなく、合格枠に入り込むには、他の受験生に得点でせりかつ必要があるのです。
一刻も早く受験生活を終わらせたいのであれば、試験対策は戦略的に臨む必要があります。
独学で勉強する場合は袋小路に陥りやすいので、専門の予備校の利用をお勧めいたします。
数ある司法書士試験の予備校のなかでも、私が推奨するのはアガルートアカデミーです。
アガルートアカデミーをお勧めする理由は、法律を始めて学ぶ方でも、短期間で戦略的に試験合格可能なレベルまで到達できるカリキュラムが用意されているからです。
既に受験経験がある方でも、アガルートアカデミーを予備校として利用しても良いでしょう。
司法書士試験に向けた予備校のなかには、対策のコースが多すぎて、合格突破のために何が必要なのかが曖昧になることがあります。
しかしアガルートアカデミーの場合は、苦手にしていることも多い、記述式試験対策が充実しているのです。
それから市販の教科書では、必要な知識と、それ以外の知識の境界を読み解くのが難しいことがあります。
アガルートアカデミーでは試験に精通した講師が、予備校オリジナルのテキストを作成することで、効率的な勉強を可能にしています。
司法書士試験は受験科目が多いだけでなく、どの科目も手抜きが出来ない側面があります。
この点もアガルートアカデミーでは、これまでの司法試験予備校として蓄積された知識と経験をもとに、戦略的に講座が設計されているので、短期合格が叶うというわけです。
さらに、仕事や学業などで予備校に足を運べない方のために、マルチデバイスでも対応しています。
場所を選ばず、どこでも受講できるメリットを享受できるのも、アガルートアカデミーならではの特長と言えます。
![]() 難関資格試験の通信講座【アガルートアカデミー】公式サイトはコチラ
難関資格試験の通信講座【アガルートアカデミー】公式サイトはコチラ
![]()
- アガルートアカデミーで後悔しないための情報《口コミでの評判を検証》のTOPページ
- 司法試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 予備試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 行政書士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 公務員試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 宅地建物取引士試験(宅建試験)の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 社会保険労務士試験(社労士試験)の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- アクチュアリー試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 弁理士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 土地家屋調査士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 測量士補試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- マンション管理士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 中小企業診断士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー
- 特定商取引法に基づく表記
